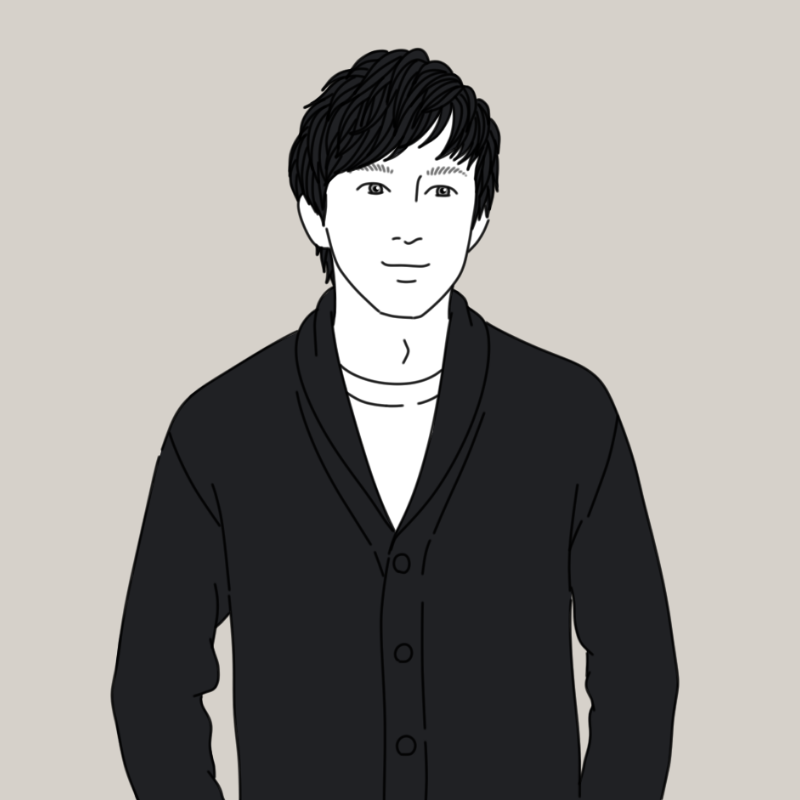
こんにちは、Marcです。
今回のテーマは「伊勢神宮の歴史や神様をわかりやすく解説」です。
神社の原点と言われる存在であり、日本人の心の故郷とも言われる伊勢神宮。しかし、実際のところ「よくわからない…」という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、



伊勢神宮って有名だけど、他の神社と何が違うんだろう…



参拝マナーは他の神社と同じ?やらないといけないこと、やってはいけないことはあるのかな?
といった疑問について、要点を絞り、神社に詳しくない方にも分かりやすくまとめていきたいと思います。
これから伊勢神宮に参拝を予定している方は、ぜひ参考にしてみてください。
伊勢神宮に近い宿を探す
\ 楽天ポイントでお得に /
\ 口コミと特集から宿探し /
伊勢神宮とはどんな神社なのか


伊勢神宮は三重県伊勢市にあり、一般的には「伊勢神宮」と呼ばれていますが、正式名称は「神宮」と言います。
一つの神社のように思うかと思いますが「内宮(ないくう)」と「外宮(げくう)」を中心とした125のお宮の総称なのです。
神話において太陽を司る神である「天照大御神」を主祭神とし、古代から神聖な場所として多くの信仰を集めてきました。
国内に約8万以上あると言われる神社の中でも「伊勢神宮」は最も尊く、日本の神社の原点とも言える存在だと覚えておきましょう。



この記事では一般的に浸透している「伊勢神宮」の呼び方で解説を進めていきます。
伊勢神宮の歴史


伊勢神宮の創建は非常に古いため、具体的な年代を確定するのは難しいとされていますが、2000年以上前に創建されたことは確実とされています。
伊勢に鎮座するまでの歴史
もともと天照大御神は代々天皇の側でお祭りされていましたが、第10代崇神天皇が皇居外に祀ることを決意。これにより現在の奈良県周辺に移ります。
第11代垂仁天皇の皇女・倭姫命(やまとひめのみこと)が、お祀りするのにより良い場所をもとめ、伊賀、近江、美濃などの国々を巡り、最終的に伊勢に入ります。
『日本書紀』によると、伊勢入りした際に天照大御神から、
この神風の伊勢の国は、遠く常世から波が幾重にもよせては帰る国である。都から離れた傍国ではあるが、美しい国である。この国にいようと思う。
引用:日本書紀
とのお告げがあったそうです。
ざっくりいうと、「都からは遠いけど、いい国だからここにいたい。」という意味です。
倭姫命は大御神の教えのままに五十鈴川の川上に宮を建てたとされています。
まだ文字で文献がまとめられるずっと前の話です。
おそらく人々の口伝伝承によりこの様な神話が伝わり、日本書紀や古事記といった国内最古の文献にまとめられる際の基となったのでしょう。
伊勢神宮の御祭神(祀られている神様)
伊勢神宮の内宮、外宮に祀られている神様(御祭神)について解説します。
内宮の御祭神


伊勢神宮の内宮(皇大神宮)は、日本で最高に神聖な場所の一つとされています。
その内宮の正宮(しょうぐう)に祀られているのは皇祖神「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」です。
皇室の御祖先であると同時に日本国民の総氏神として崇められる神様です。
内宮の域内には、天照大御神が祀られている正宮の他に、2つの別宮も鎮座しています。
- 荒祭宮
-
天照大御神の荒御魂(あまてらすおおみかみのあらみたま)
- 風日祈宮
-
風を司る御祭神(国生みの神である伊弉諾尊の御子神)
- 級長津彦命(しなつひこのみこと)
- 級長戸辺命(しなとべのみこと)
- 氏神
-
同じ地域(集落)に住む人々が共同で祀る神道の神様のこと。
- 荒御魂
-
神様の荒々しい側面や荒ぶっている魂のこと。
内宮についてもっと詳しく


外宮の御祭神


外宮(豊受大神宮)の正宮に祀られているのは「豊受大御神(とようけおおみかみ)」です。
天照大御神の食事を司る神様であり、五穀豊穣、衣食住をはじめとした産業の守り神と言われています。
外宮の域内には、豊受大御神が祀られている正宮の他に、3つの別宮も鎮座しています。
- 多賀宮
-
豊受大神荒御魂(とようけおおかみのあらみたま)
- 土宮
-
地元・山田原の鎮守神である大土乃御祖神(おおつちのみおやのかみ)
- 風宮
-
風を司る御祭神(国生みの神である伊弉諾尊の御子神)
- 級長津彦命(しなつひこのみこと)
- 級長戸辺命(しなとべのみこと)
外宮についてもっと詳しく


伊勢神宮の自然


伊勢神宮には「神宮備林」と呼ばれる檜(ひのき)や杉(すぎ)などの針葉樹を主体とした森林があります。
その森林は、神々に捧げる祭具や建材として使用される木材を提供すると同時に、周辺の自然環境の保全にも貢献しています。
また、多くの野生動物の生息地でもあり、豊かな自然の中で多種多様な生態系の営みを見ることができます。



境内の木々は樹齢数百年を超えるものが多く、その光景は圧巻です。その豊かな自然環境と神々が住まうお宮に日本の原風景を見ることができます。
伊勢神宮と人々の信仰


伊勢神宮への参拝は「お伊勢参り」や「お蔭参り」とも呼ばれ、古代より時代時代の人々の文化的習慣として行われてきました。
特に江戸時代には庶民にも広く普及しましたが、交通が発達していない当時は、江戸からは片道15日間、大阪からでも5日間、名古屋からでも3日間の道のりを徒歩で向かうしかありません。
当時の人々にとって「お伊勢参り」は一生に一度の大きな旅としてあこがれの対象だったようです。
当時の参拝は、二見浦(二見興玉神社辺り)で禊をして身を清め、その後に外宮と内宮を参拝し、最後に朝熊岳に登る、という流れで行われていました。
伊勢神宮の式年遷宮とは?


伊勢神宮には「式年遷宮(しきねんせんぐう)」という伝統的な神事があります。
これは20年ごとにお宮を一から建て直し、神々を新たなお宮に移す儀式です。
この儀式は「再生」「蘇り」「永遠」の象徴でもあり、少なくとも7世紀から続いています。




式年遷宮が近づいたお宮は苔むす姿で、自然と一体化したような荘厳さがあります。
一方、式年遷宮後の建て替えられたお宮は神々しく輝いて見えます。
このような、式年遷宮前後のお宮の違いを楽しめるのも伊勢神宮の魅力の1つです。
伊勢神宮を参拝する際の注意点


伊勢神宮は特別な神社ゆえ、他の神社参拝と少し異なる点があります。
いくつかの注意点があるので、参拝前に必ず抑えておきましょう。
内宮を参拝する前に外宮を参拝する
神宮の祭典は、まず外宮で祭儀を行う「外宮先祭」と言われる習わしがあります。
その順序にならい、外宮から参拝するのが一般的です。
また、内宮・外宮どちらかしか参拝しないことを「片参り」と言いいます。
片参りはあまり縁起が良くないとされているので注意しましょう。
正宮でのお賽銭は禁止
他の神社と大きく違う点としては、正宮での「お賽銭禁止」が挙げられます。
本来、伊勢神宮は皇祖神である天照大御神をお祀りするところであるため、天皇陛下以外が幣帛(へいはく)をお供えすることを禁止した「私幣禁断」という制度がありました。
現在では一般人も参拝できるようになりましたが、当時の名残で正宮にお賽銭箱はありません。
しかし、それでもお賽銭投げ入れる人が多いことから、神殿を守るために白い布が敷かれるようになったと言われています。
お賽銭したい場合は正宮参拝後の別宮参拝の時にしましょう。
- 幣帛
-
神道の祭祀において神に奉献する、神饌(みけ)以外のものの総称。
- 御饌
-
お祭りなどで神様に献上するお食事のこと。
個人的な願いごとよりも公な願いごとを
一般的には、神社に参拝すると「無病息災」「家内安全」「合格祈願」といった個人的なお願いごとをすることが多いのではないでしょうか。
しかし、伊勢神宮は天皇陛下が天照大御神に国民の幸せを祈るお宮であり、個人的な願いごとより公な願いごとをする方が良いと言われています。
個人的ではないお願いごととは、具体的に言うと以下のような内容です。
- 天照大御神への感謝
- 皇室や国家の弥栄(繁栄)
- 日々の暮らしへの感謝
参拝した際は、個人よりももっと大きな「公」を意識して祈りを捧げましょう。
個人的なお願いごとは荒祭宮と多賀宮でする、というような地元の風習としての信仰もあるそうです。



参拝前に公式サイトの参拝作法とマナーもしっかりチェックしてくださいね。
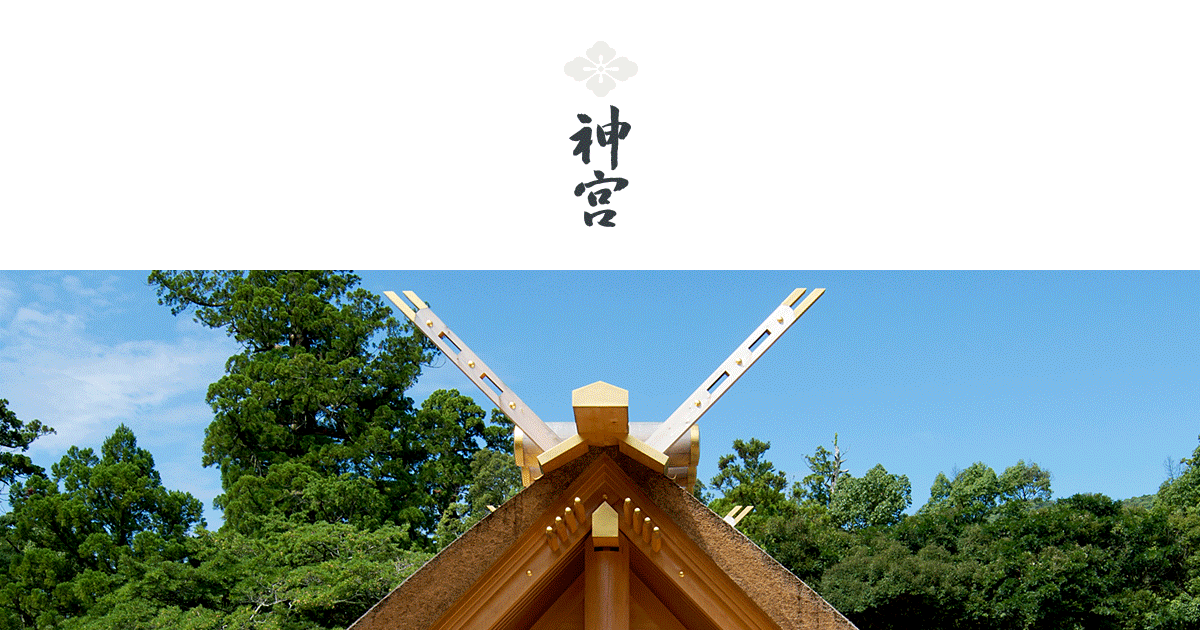
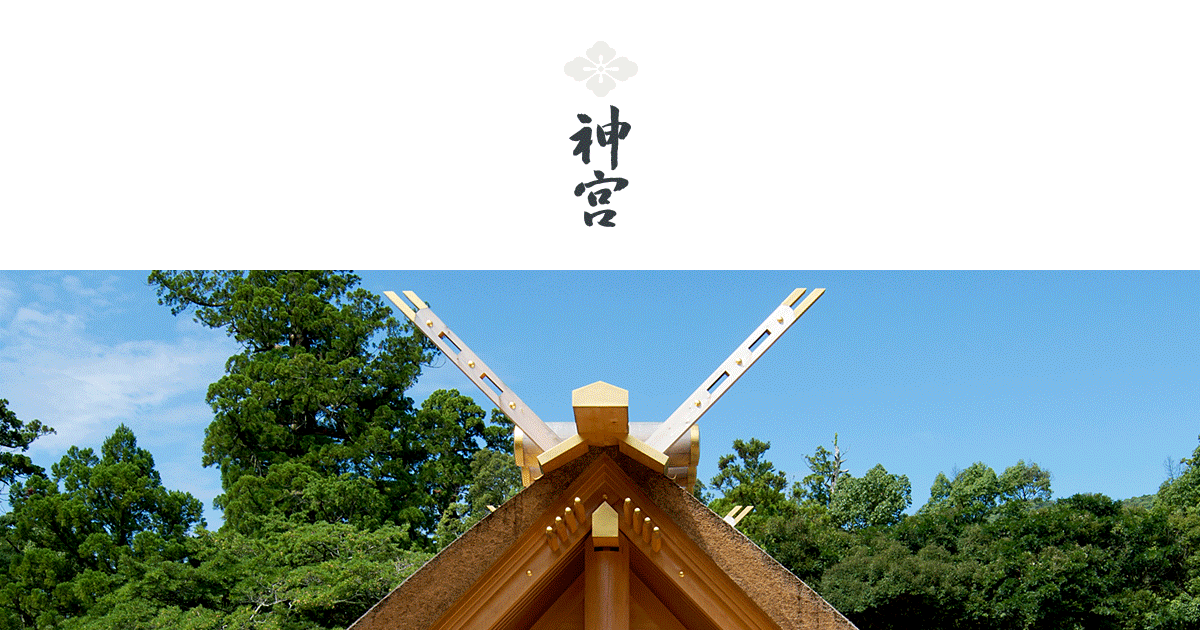
まとめ


最後に本記事のまとめです。
- 正式名称は神宮
- 一つの神社ではなく、内宮・外宮を中心とした125のおみやの総称
- 全国の神社の中心的かつ最も尊い存在
- 内宮の御祭神は天照大御神、外宮の御祭神は豊受大御神
- 参拝順序は外宮→内宮
- 正宮はお賽銭禁止
- 個人的なお願いごとではなく公なお願いごとを
- 20年ごとにお宮を一から建て直す「式年遷宮」という神事が行われている
あくまではじめての参拝を想定してこの記事を執筆しましたが、歴史が深く、神道の根本であることからまだまだ知っておきたい情報は山程あります。
もし興味を持っていただけたら、本記事を執筆時に参考にさせていただいた以下のサイトもぜひご覧ください。
より伊勢神宮についての理解を深めることができますよ。



僕自身も何度も訪れていますが、実際に行ってみると「特別」の意味も納得!
自然に囲まれた美しいお宮を目の当たりにすると、その荘厳さに魅了されてしまうはずです。
まだ参拝したことがない方は、機会を見つけてぜひ参拝してみてください。
伊勢神宮に近い宿を探す
\ 楽天ポイントでお得に /
\ 口コミと特集から宿探し /












